聖なるイチジクの種は他の木を糧に育ちその後その木を絞め殺す…
昨年2024年のカンヌ国際映画祭で審査員特別賞を受賞し、今年3月2日に開催されるアカデミー賞では国際長編映画賞にノミネートされています。ただし、イランからではなくドイツ代表としてです。監督はイランのモハマド・ラスロフ監督、2020年に前作(かな…)の「悪は存在せず」がベルリン国際映画祭で金熊賞を受賞しているとのことですが見ていないなあと思いましたら、映画祭で上映されただけで劇場公開されなかったようです。
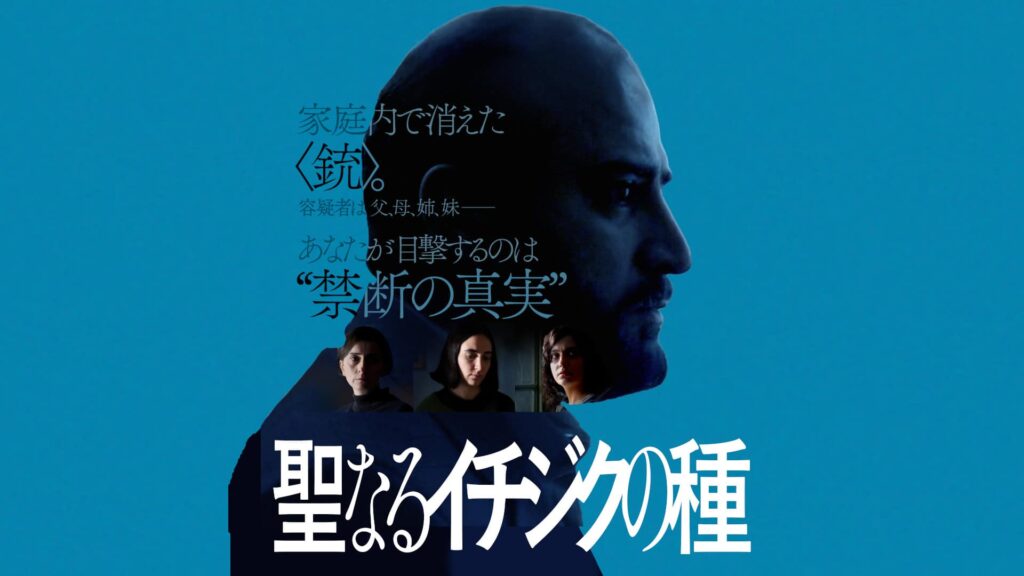
スポンサーリンク
イランでは映画製作も命がけ…
どの国でも反体制的な映画を撮ることには勇気がいるものですが、イランにおいては命がけということになります。
モハマド・ラスロフ監督は幾度も逮捕され有罪を言い渡されています。ウィキペディアもその言語によって記述にズレがありますので何言語かを見てみたんですが、結局そのズレはそれだけ幾度も逮捕されていることから生じているようです。
2010年にジャファル・パナヒ監督とともに逮捕され懲役6年の刑(執行されなかったよう…)、2017年には「ぶれない男 The Man of Integrity」に関連して出国禁止、その後2019年には懲役1年の刑を宣告され、2020年「悪は存在せず」が金熊賞を受賞した際には渡航できず、その後「体制に反対するプロパガンダ」となる映画3本を制作したとして懲役1年と2年間の映画製作禁止が言い渡されています。2022年に警察批判の記事を発表して逮捕され、後に保釈されていますが出国禁止、そして2024年にはこの「聖なるイチジクの種」に関して懲役8年、鞭打ち、罰金の判決を受けています。
という経歴のあるラスロフ監督、ついにイラン脱出を決断したのでしょう。カンヌでの上映の直前とありますので昨年の春先のことだと思いますが、28日間かけてイランを脱出しドイツに渡ったそうです。
そして、カンヌ国際映画祭でのプレミア上映には娘役の二人とともに両親役の二人の写真を持って登壇しています。IMDbにはその写真もありますが下はウィキペディアからです。右の二人がレズワン役のマフサ・ロスタミさんとサナ役のセターレ・マレキさんです。左の二人が出演者だとしますとレズワンの友人役と母親のナジメが相談する女性ですかね(未確認…)。

John Sears, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
スポンサーリンク
秘密裏に撮られたのかもしれない…
この映画を今の日本の価値観で見れば、なにゆえ懲役8年?と感じる映画です。それが現実なんですから何を言っても空虚なだけですが、それだけイランの公権力が神経質になっているということなんでしょう。
映画は前半と後半でガラリとトーンが変わります。前半は、実際に2022年9月13日に起きた事件、当時22歳のマフサ・アミニさんがヒジャブを適切に着用していないとして逮捕され、その後死亡した事件をきっかけに大規模に拡大した抗議行動を背景にして、その緊迫感がある家族内に波及する様子が描かれています。この前半はかなり見られます。
後半はその家族間の夫婦、親子関係にイランの社会体制を比喩的に反映させてドラスティックに描いています。一見前半に提示された問題とは関係なく進むようにみえますが、そうではなく前半の家族内の軋みが実はその置かれている社会体制の反映であることをみせているのだと思います。
ただ問題は、後半の描き方がかなり過剰であり、何を思ったかエンタメ要素かと思うようなつくりを取り入れていることです。それがためにかなり映画としての質を落としています。
なお、この映画、全般を見渡してみますと、登場人物もかなり限定されていますし、その多くが室内で進行します。また、後半は人里離れたロケーションで撮られています。おそらく映画製作を公にして撮ることができなかったからではないかと思います。撮影も秘密裏に行われたのかもしれません。
スポンサーリンク
前半はナジメの心理状態から緊迫感あふれ…
ある家父長制の家族、イマン(ミシャク・ザラ)とナジメ(ソヘイラ・ゴレスターニ)の夫婦に長女レズワン(マフサ・ロスタミ)と次女サナ(セターレ・マレキ)の姉妹、4人家族の物語です。レズワンは大学への進学云々といっていましたので18歳くらい、サナは15、6歳の設定じゃないかと思います。
映画冒頭は政府組織で働くイマンが予審判事に昇進し、ナジメもイマンの20年来の願いがかなった、娘たちにも個室を与えられると喜ぶことから始まります。ただ、それもかなり抑制的です。つまりイマンもナジメも自分たちが体制側に所属しておりそれを敵対視するものがいることを自覚しているということです。娘たちには父親がどんな仕事をしているのか話していなかったと言っています。
イマンは上司から護身用にと拳銃を支給されます。これが後半のプロットのキーになります。また、この前半ではイマンは脇に置かれた立場になっており、しかしながら後半のかなり異常とも思える行動の伏線的な心理状態が準備されます。昇進は決して喜ぶべきものではなく、何の取り調べもせずに死刑を求刑するよう強要される立場になったことを思い知らされるのです。
できるならばこの前半でイマンがどんどん精神的に追い詰められていく様を描いておけば後半の異常さの説得力も増したのだと思います。仕事から疲れて家に帰るシーンはありますが、その多くはナジメが娘たちの危うい行動をイマンに知られたくないと考えている流れの中ですので、あまりイマンの心情が浮かび上がってくることはありません。職場のシーンがあればとは思いますが、それもこの映画制作の置かれている環境のせいかもしれません。
ということで前半はナジメと娘たちの関係が軸になって進みます。
生活環境としては中流家庭の印象です。住まいは2DKくらいで娘たちは二段ベッドで寝ています。よくテレビから国営放送のニュースが流れています。しかし娘たちはスマートホンを持っていますので情報はネットからやってきます。価値観はほぼ我々と同じようです。ヒジャブも強制と感じているようですし、サナは髪を染めたいとも言っています。そして、マフサ・アミニさんの事件と明示されているわけではありませんが、そのとき実際にネットに流れていた抗議活動を弾圧する警察権力の暴行映像が頻繁に挿入され、娘たちはその映像を見ているということです。テレビのニュースが女性の死因は心臓発作だと報じても娘たちは嘘だと考えています(知っています…)。
娘たち本人が抗議活動に加わるシーンはなく、レズワンの友人によって家族間に波風が立ちます。レズワンがその友人を家に泊めようとします。ナジメはイマンに知られたら大変なことになるからダメだと言います。ナジメが恐れているのは自分たちが権力側に属していることが知られ敵対視されることです。ナジメとしては今の生活を守ることが最優先であり、また家族間は穏やかでありたいと願っています。結局ナジメは妥協し、イマンに知られないよう部屋から出ないことを条件に一泊させることを認めます。
後日、その友人が抗議活動に巻き込まれ(とレズワンは言っている…)顔に大怪我をします。レズワンは家につれてきて匿います。友人は病院に行けば逮捕され拷問されると言っています。ナジメが散弾銃の玉を取り出し応急処置します。そして翌日友人は自ら出ていきます。
この友人のその後は忘れ去られていますが、台詞として逮捕されたというようなことがあったように思います。こうした中途半端さもロケできないなど(想像です…)かなりの制約の中で撮られていることからでしょう。
結局この前半では、それがラスロフ監督の意図であるかどうかはわかりませんが、ナジメの意識が映画の前面に出ており、つまり、この生活を守りたいのに娘たちが言うことを聞かない、そしてそのことをイマンに知られたくないという意識を感じさせる結果となっています。
ですので、娘たちがシンパシーを感じている反体制意識に共感するよりも娘たちの行動がある種わがままにも見えてきます。その結果として家庭内に生まれる緊迫感を強く感じさせるということです。
スポンサーリンク
後半は比喩的に社会体制が家庭内に反映され…
後半になりますと抗議活動のことはほぼ忘れ去られ、イマンに支給された拳銃がなくなることで物語は進みます。
いつも夫婦のベッド脇のチェストに入れている拳銃がなくなっています。イマンはこれまでの20年が無駄になったとパニックぎみです。前半にはバスルームに置きっぱなしになっている拳銃をナジメがチェストにしまうシーンが入れてあり、ナジメがそのことや職場に忘れてきたのではないかと言っても聞き入れず家族を疑い始めます。
ここからはかなり異常で日本の価値観ではちょっと思いつかないようなシーンが続きます。それもかなり冗長です。
簡単に書きますと、イマンはまず上司に相談します。上司は尋問が専門の同僚に調べてもらえと言います。イマンは妻と娘二人を連れていきます。そしてナジメと娘たちがまるで容疑者のように尋問されます。あの一連のシーンはラスロフ監督の体験からつくられているのかもしれません。目隠しをされて無言で紙に書くことをうながされるシーンはかなりリアルでぞっとします。
尋問の結果、レズワンが盗んだということになったようです。これ以降、この家族は比喩的に、権力側のイマン、抑圧弾圧される側の娘たち、そしてある種良識派としてのナジメという立場に置かれていきます。
このことをナジメは娘たちに父親の本性(字幕…)を知られたくなかったと言っています。そして映画はシャイニングになります。内容として入れづらいですのでやめていますが「シャイニングになります(笑)」と入れたいところです。
突然、イマンの個人情報がネットにさらされたとなります。私は上司や組織の仕業でイマンがそれと戦うのかと思いましたら、おそらくこれも限られた映画制作環境のせいかとは思いますが、家族そろってテヘランから逃げ出し、一気にロケーションが人里離れた田舎になります。そして映画はアクション映画によくある車を敵の車にぶつけるカーアクションになります。
ガソリンスタンドでイマンたちを撮影する者がいましたのでイマンが追いかけてスマートホンを取り上げていました。相手はバールのようなもので、イマンは拳銃(上司から借りた…)で対峙しながらお互いの妻がスマートホンで撮影し合うシーンは面白かったです(映画として…)。
で、イマンたちはイマンの生まれ故郷の田舎の一軒家に到着します。そして、この後30分くらいでしょうか、イマンは妻や娘たちにカメラを向けて尋問し、それぞれ部屋に閉じ込め、その後逃げ出した3人を拳銃を持って追い回し、映画は完全にシャイニングになります。
結局、拳銃を盗んだのは妹のサナでした。ただ、その理由やそもそも拳銃を盗んだことの意味合いにも大した意味をもたせることができずに最後はイマンが穴に落ちて死んでしまいました。サナは発砲していましたので撃たれたということかもしれません。
いまウィキペディアのプロットを見てみましたら、サナがイマンの立つ地面を撃ったために地面が崩れて落下したということらしいです。
映画冒頭にあった「聖なるイチジクの種」が他の木を糧に育ちその後その木を絞め殺すという逸話の意味が映画に反映されているとしますと、社会体制、具体的にはイランのイスラム支配体制が家庭にまで入り込み家庭、ひいては社会を崩壊させるということなんでしょうか。
という映画、制約された制作環境で撮られたのであろうとの想像を前提にすれば、また後半も前半のトーンでまとめあげてていればとてもいい映画になっていたと思います。
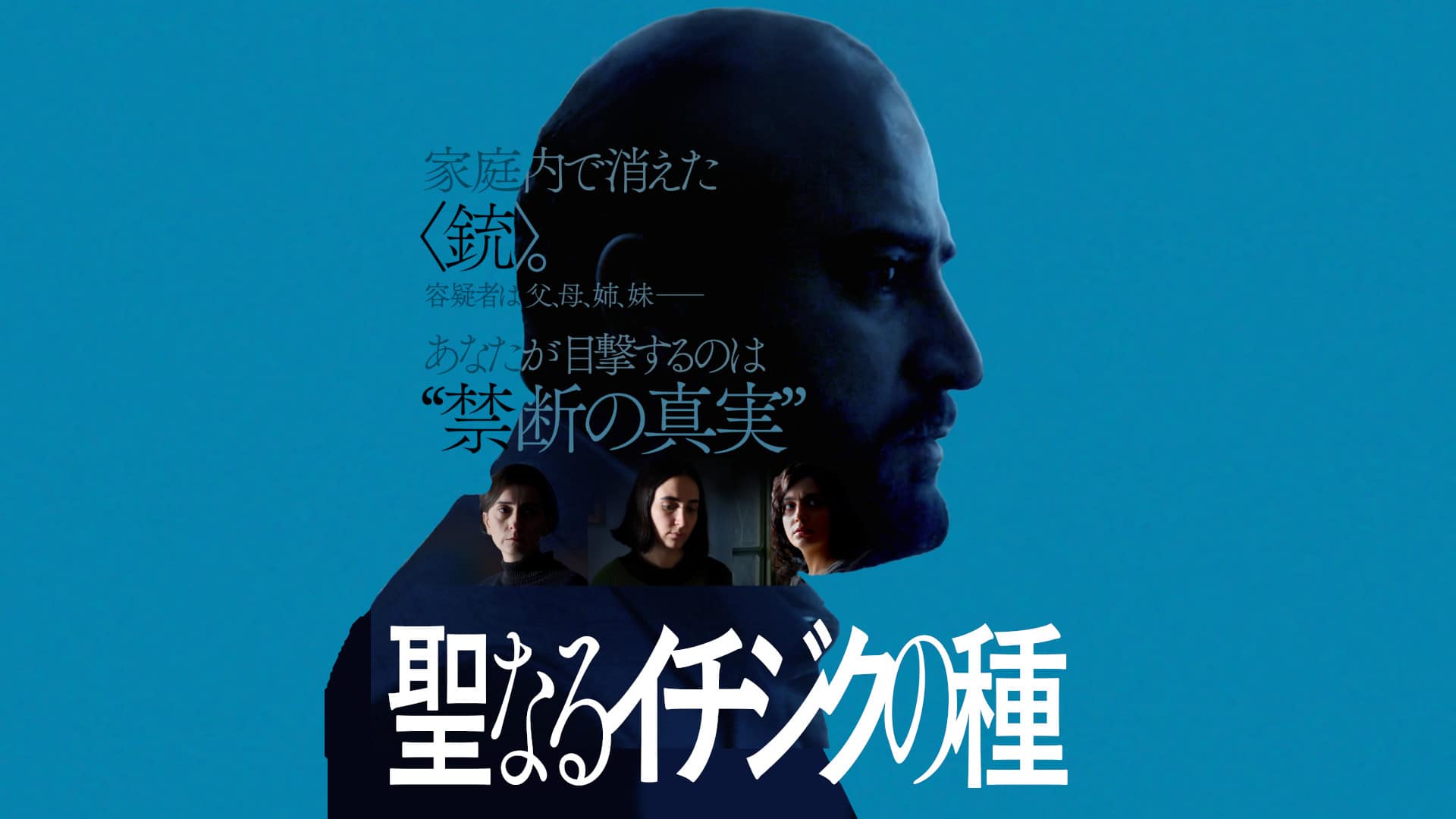

![ペルシャ猫を誰も知らない [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51CeWldjIzL._SL500_.jpg)