鬼滅に占領されたシネコンを逃れて配信の大海原(?)へ…
シネコンが鬼滅に占拠されていますね。ここ数日、劇場の予約サイトにすんなりと入れません(涙)。まあ結局、今週公開作にそそられるものはなかったのでいいんですが、それにしてもその興味や欲望(?)はもう少し他のものにも散らばらないんですかね。
ということで、配信で「羊と鋼の森」を見てみました。
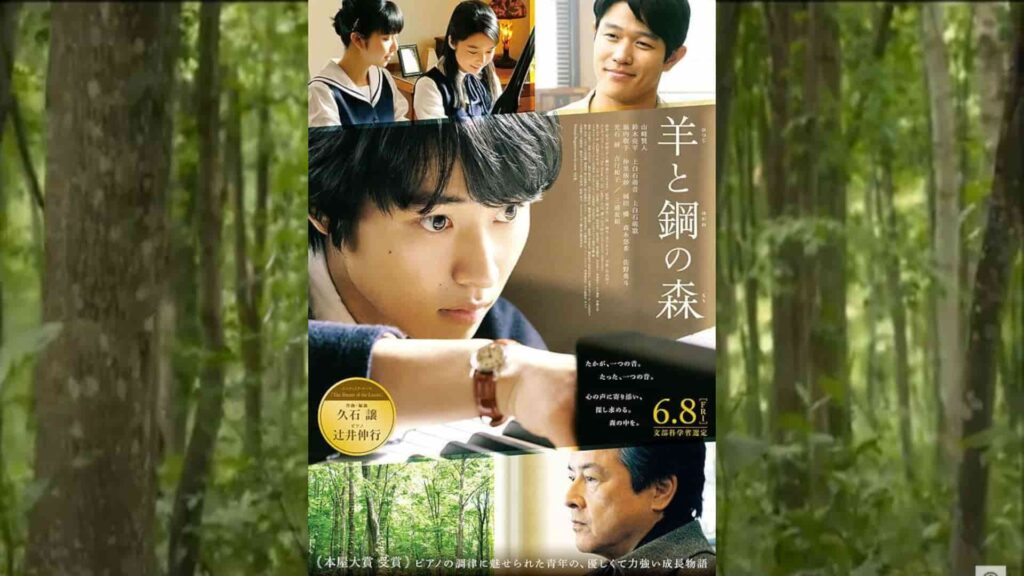
スポンサーリンク
ピアノの響きから森の連想に驚く…
え、こんな話だったの?
「羊と鋼の森」のタイトルは原作が本屋大賞ということで知ってはいたんですが、こんな話だとはちょっと驚きました。
ピアノ調律師の成長物語で、ピアノの音は羊の毛でできたハンマーで鋼の弦を叩くことから生まれるという意味からの「羊と鋼」であり、さらに驚くことにその音に「森の匂い」を感じるという話なんです。
ピアノの音と言いますか響きと言ったほうがいいかとは思いますが、ピアノの調律から森を連想するという感性に驚いたということです。
原作は宮下奈都著『羊と鋼の森』、2016年本屋大賞受賞作です。Audible版もあり、内容的にも通勤通学中に聴くのに向いていそうです。
スポンサーリンク
その肝心の森のシーンが…
この映画を見てみようと思ったのは橋本光二郎監督の名前が目に入り、すぐには思い出せなかったのですが「小さな恋のうた」のタイトルが目に入り、その映画にいい印象が残っていたからです。
で、「羊と鋼の森」です。映画冒頭のナレーションは原作のままだったようです。
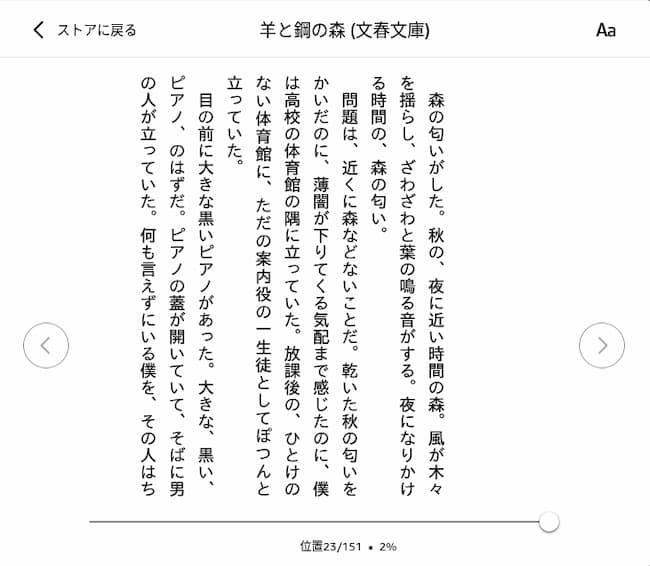
高校生の直樹(山﨑賢人)が調律師板鳥宗一郎(三浦友和)を体育館のピアノに案内するところから始まります。
直樹は、板鳥がピアノのハンマーの「羊」を調整し「鋼」の弦を叩く音を聞き「森の匂い」を感じます。
原作の書き出しでもあるこのシーンは、フィックスで撮った森の中に直樹が歩いて入っていく画で表現されています。直樹の家は林業を営んでいますので子どもの頃から木々のざわめきや緑の匂いの中で育ってきたんだろうと思います。でも、そんな感じがしないんです。ナレーションの言葉と画がぴったりとは感じられず、言うなれば旅行者が森の中に入っていくようにしか見えないんです。
映画的に物足りないということです。音の響きに合わせてなにか動きがあるとか、直樹の見ているものを画にしたほうがいいと思いますけどね。まったくもって余計なことではありますが、森のシーンになるたびに同じことを感じた映画です。
スポンサーリンク
直樹の成長の過程が見たいけど…
高校を卒業した直樹は調律師になるために両親を説得して専門学校へ入ります。
この両親を説得するシークエンスには、祖母が庭の椅子に座って森を見つめており、そこに直樹が森から戻ってくるというシーンがあり、なにか会話が交わされるのかと思っていましたら何もなかったですね。
この祖母は後半に亡くなるわけですが、その際直樹が駆けつけるというひとつのドラマになっており、またその後の弟とのやり取りでも直樹と祖母のシーンが使われていたりします。映画的にはそれなりに存在感を持たされているのにぼんやりした存在のまま終わっていました。
原作の静謐さ(読んでいないけど多分…)に囚われ過ぎたのかもしれませんね。
直樹は専門学校卒業後、板鳥の楽器店に就職し調律師として一歩踏み出します。楽器店には先輩調律師の柳(鈴木亮平)と秋野(光石研)がいます。直樹は柳について調律の現場を経験していきます。
柔らかい音、硬い音、響く音、包み込むような音、調律によって音が変わるのです。単に音程だけではないんですね。ハンマーの「羊」に針を刺して調整するシーンや、後半の著名音楽家のコンサートシーンでは板鳥がピアノの足のキャスターの向きを変えて演奏家の要望に応えていました。理論的には理解できますが問題は違いを聞き分ける耳ですね。
映画の軸となっているのは天才姉妹との関係です。和音(上白石萌音)は努力型の神経質タイプ、由仁(上白石萌歌)は楽天的な天才肌です。
柳について調律の難しさを学んでいたある日のこと、直樹は由仁に鍵盤が戻らないんですと呼び止められて修理に向かいます。鍵盤は戻りますがここの音程がおかしいと言われ、やや迷いを感じながらも調律に挑戦します。しかし、触れば触るほどまとまりがつかなくなってしまいます。パニック状態です。柳に電話して助けを乞い、姉妹には明日柳がきますと謝罪してその悪夢のような状態から逃げ出します。
時は過ぎ、とは言っても直樹の自信なさげはあまり変わらないんですが、とにかく姉妹のピアノの調律を任されるまでになっています。そして姉妹のピアノコンテストの前の調律に向かいます。和音の細かい要望に答えて調律し、帰宅した由仁にもいい調律ですと言われて安心して帰ってきます。
しかし後日、姉妹の家から調律をキャンセルしたいと電話が入ります。理由は娘がピアノを弾けなくなったということらしいのですが、なぜか直樹は自分が和音に合わせて調律したからと思い込み(ってよくわからないけど…)雪の外へ飛び出していきます。思い上がりだと柳に止められます。
この姉妹の話の間に、両親を亡くしたために引きこもってしまった青年が直樹の調律で再起する話とか、横柄なピアニストの話とか、直樹の両親を説得した回想とか、柳が婚約する話とか、板鳥から調律の極意(?)を聞きチューニングハンマーをもらう話とか、柳がメトロノームの刻む音で心を落ち着ける話とか、秋野はピアニストへの道を挫折した調律師であるとか、祖母が亡くなるとか、著名ピアニストが板鳥を調律師に指名してきたといった話が挿入されています。
そして、由仁がピアノを弾けなくなったのはピアノに向かうと指が動かなくなる病気だと明かされ、それがために和音もピアノを弾こうとしなくなったことがわかります。
柳は和音に自分の結婚披露パーティーでピアノを弾いてほしいと依頼します。そして、直樹にそのピアノの調律を命じます。パーティーの日、和音は音が響かないと言います。直樹は板鳥がやったようにピアノの足の向きを変えて調整します。そしてパーティーではみな和音のピアノに耳を傾けています。
和音はプロのピアニストを目指すと言い、由仁は調律師になると言い、そして直樹はコンサートチューナーを目指すと宣言して終わります。
スポンサーリンク
パーティーシーンのエンディングに違和感…
原作も柳の結婚披露パーティーがエンディングなんですかね。
あのガラス窓のレストランで、おそらく床は磁器タイルとか塩ビタイルとかだと思いますし、そもそもがやがやするのが当たり前と言いいますか、それが目的のパーティーに、言っちゃなんですがコンサートホールのような演出を持ち込んでいることにすごい違和感を感じます。
とにかく、いろんなところにつくりもの臭さと中途半端さを感じる映画です。
一連の姉妹のドラマ展開もぎこちないのですが、引きこもりの青年のシーンとか、見え見えの横柄な見栄っ張りのピアニストを出しているところとか、もう少しシンプルに直樹のリアルな成長物語にしないと映画的じゃないですね。
祖母の存在の中途半端さはすでに書きましたが、秋野がピアニストを諦めたことや柳のメトロノームについてももっと深めればいいのにと思います。
原作がどうなっているのかはわかりませんが、これはシナリオの問題ですね。
原民喜著『砂漠の花』からの引用
明るく静かに澄んで懐しい文体、少しは甘えてゐるやうでありながら、きびしく深いものを湛へてゐる文体、夢のやうに美しいが現実のやうにたしかな文体
(青空文庫)
も生きていませんね。
パソコンのモニターで見てちゃ、よほど集中できる映画じゃないとだめですね。


