ピアニストはゴドーになり得たか…
七里圭監督の名前がふっと目に入りましたのでポチッとしてみました。久しぶりです。
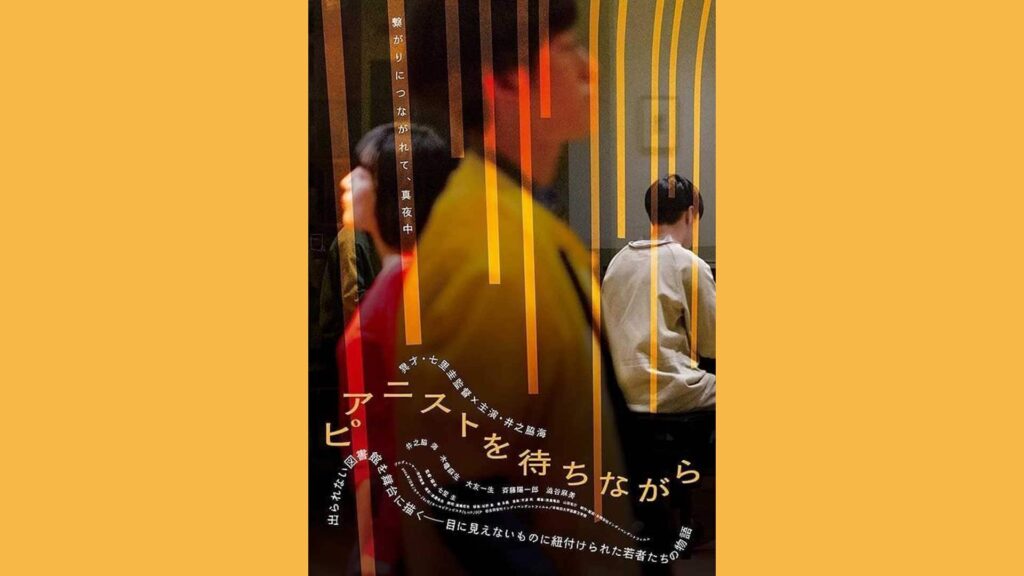
スポンサーリンク
ゴドーを現代に置き換えた?…
「ピアニストを待ちながら」ですから当然「ゴドーを待ちながら」が意識されているわけですが、こういうのはなんて表現するんでしょうね。映画の批評によく使うオマージュというものとはちょっと違いますので、現代的解釈? いや、解釈してるわけではありませんので、現代に置き換えた? 今風に言えば上書き、そんな感じですかね
「ゴドーを待ちながら」はもう様々に解釈され尽くしているとは思いますが、一番オーソドックスなのは「不在」じゃないかと思います。ゴドー(Godot)をゴッド(God)と解釈して神の不在云々というのは今ではさすがに陳腐と言われそうですが、ただ、ウラジミールとエストラゴンの二人が何か(誰か)を待っていることには間違いないわけですから、その「何か」に注目すればその「何か」はやってこないわけですから「不在」になります。もちろん、待っているその行為に注目したり、無意味に思える会話に注目したりすればまた違った解釈ができる戯曲だとは思います。
いずれにしても様々に解釈されて他分野にまで波及していくわけですからすごい作品ということではあります。
で、この「ピアニストを待ちながら」ですが、これも同じように解釈されることを求めるような作品になっています。正直なところ面倒くさいなあとは思いますが(笑)、そういう映画ですから仕方がありません。
さすがに他分野にまで波及するような力はなさそうです(ゴメン…)。
スポンサーリンク
不在というよりも不確実性かな…
瞬介(井之脇海)が倒れています。「瞬」にもこだわっていますね。
村上春樹ライブラリーと呼ばれる早稲田大学国際文学館で撮っているとのことですので図書館ということになるのかも知れませんが本が生かされたシーンはありませんので特に意味はないと思います。調べていませんがそこで撮ることが前提じゃないかと思います。
もしそうだとすれば、発想の源としては村上春樹さんが「不在」を書く小説家ですので、「村上春樹ライブラリー」 → 「不在」 → 「ゴドーを待ちながら」ということかもしれません(勝手な想像です…)。
自動ドアがあり、その開閉音が強調されています。外に出られないのか、あるいは出ようとしないのかも知れませんが、閉ざされた空間であることが提示されます。
その空間で瞬介が過去に一緒に劇を上演しようとしていた行人(大友一生)と貴織(木竜麻生)に出会って話をしたり、その劇の一部のような振りの動きをしたりします。また、瞬介との関係はよくわかりませんが、絵美(澁谷麻美)と出目(斉藤陽一郎)という人物が登場するという内容です。
これじゃなんだかわかりませんね。今、出演者の名前を調べようと公式サイトを見ていましたら、「ピアニストを待ちながら」というのは過去に行人の作演出で上演するつもりだった劇のタイトルということのようです。
という設定で話は進むわけですが、不条理劇とすることが意図されているわけですから、台詞にしても行為にしても個々の意味や関連性を考えてもあまり意味はないと思います。基本は過去に3人で「ピアニストを待ちながら」という劇を上演しようとしていたが何らかの理由でできなかったということが軸となっているようです。
テーマは「不在」とはちょっと違いますね。「ピアニストを待ちながら」といってはいますが、ピアニストが来なかったから劇が上演できなかったわけでもなさそうですし、映画の中でもピアニストのことはさほど話題になっていませんし、実際瞬介の弾くピアノで行人と貴織は振りのついた動きをしています。
「不在」よりも「不確実性」かもしれません。
ということでいきなり結論ですが、現代人は時間的にも空間的にも人間関係的にも不確実性の中に置かれているということがテーマじゃないかと思います。
なんて考えていましたら、公式サイトに答が書いてありました(笑)。
このおかしな物語は、私たちが経験したコロナ禍や、今や当たり前になったオンライン、SNSでの非対面コミュニケーションの奇妙さを暗示している。20世紀の不条理は、すでにリアル。私たちは、いつも不在の相手につながれて、待たされて、くたびれている。サミュエル・ベケットの有名戯曲を思わせる題名に、その意図が込められている。
(映画『ピアニストを待ちながら』公式サイト)
という映画でした。
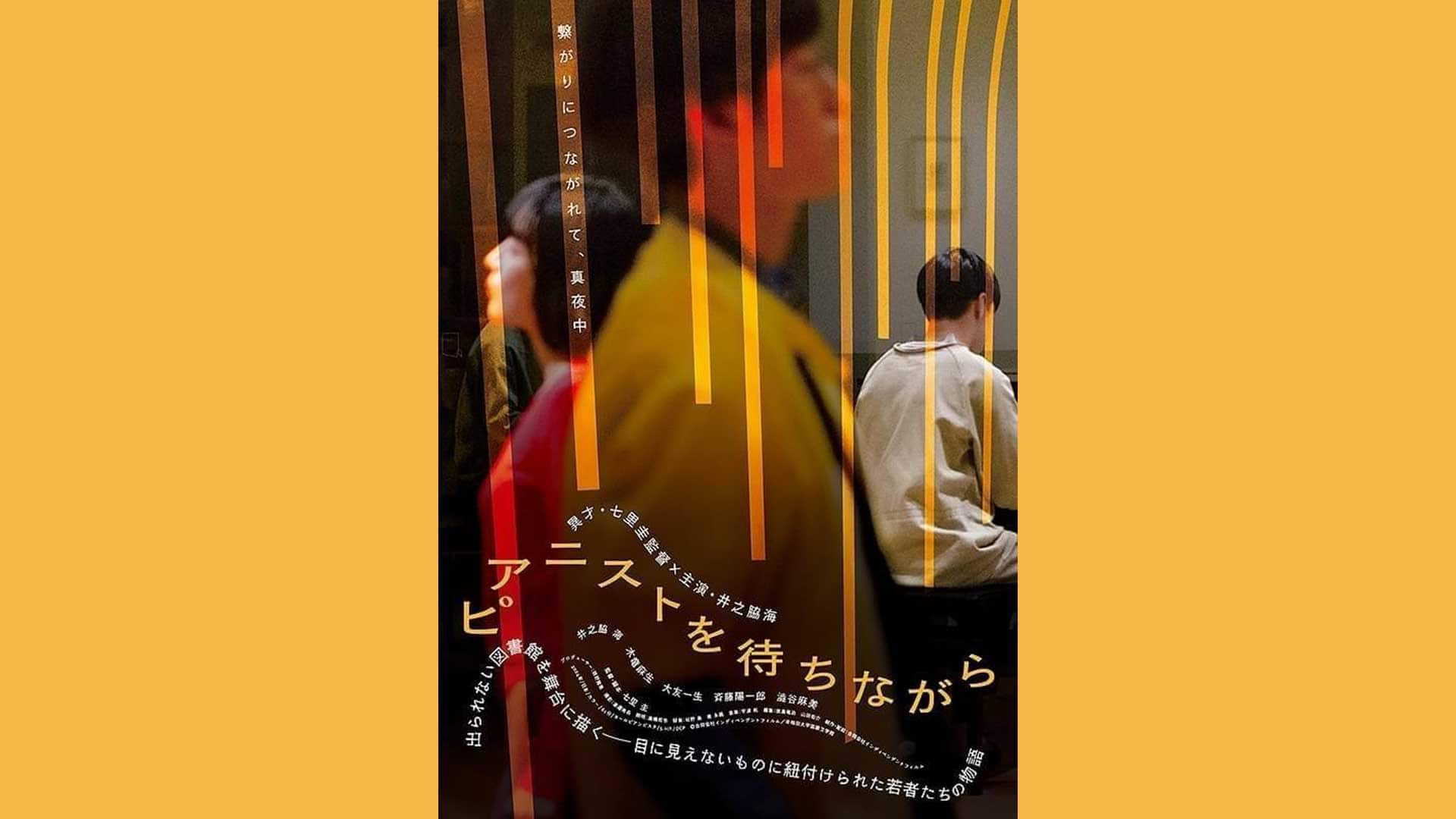

![のんきな姉さん [VHS]](https://m.media-amazon.com/images/I/51pzKWPkJnL._SL500_.jpg)