感じさせるだけの情感もなく、考えさせるだけのわかりやすさもなく…
何度見せられたかわからない予告編以上のものはあるのか? と思うくらい印象深い予告編、そして音楽という映画です。アウシュビッツを描いた映画は数え切れないほどありますが、まだこうした切り口があったかと期待は高まります。
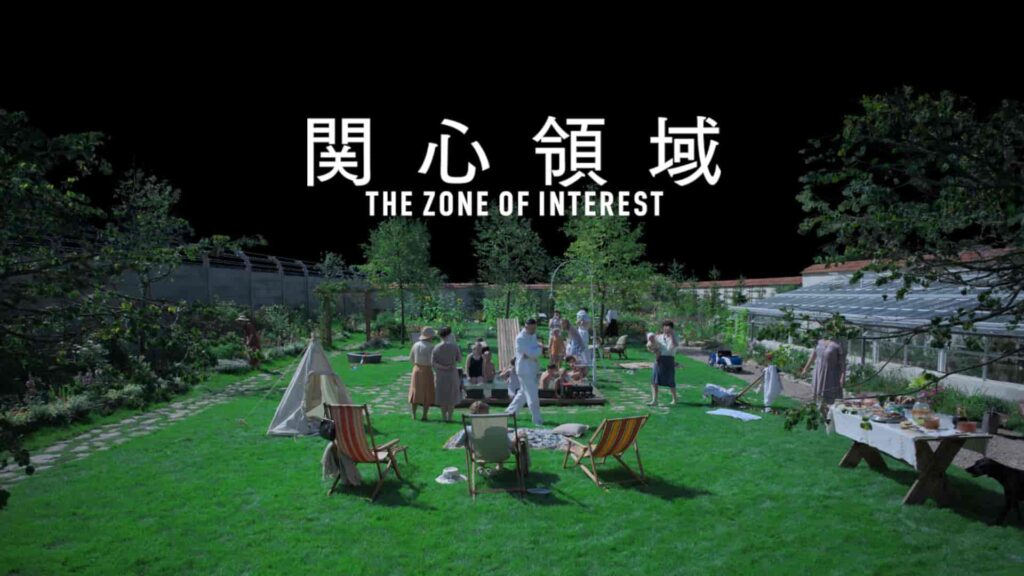
スポンサーリンク
感じさせるほどの情感はなく…
残念ながら切り口は目新しくても映画自体に予告篇以上のインパクトはありませんでした。それに、アウシュビッツの隣の牧歌的な空間というものを見ていてもアウシュビッツ絶滅収容所の実相がみえてくるわけでもなく、また、ルドルフ・ヘスやヘートヴィヒ・ヘスは無関心の犯罪者ではなく確信犯です。
一番の問題は映画自体(というよりシーン、映像…)にわかりにくいところが多いことで、日本の公式サイトに何かあるかと見てみたんですが何もありません(笑)。それに「時は1945年」とありますが、1943年の間違いですね。
ルドルフ・ヘスがアウシュビッツの所長を務めたのは 1940 年 5 月 4 日から 1943 年 11 月 10 日までと 1944 年 5 月 8 日から 1945 年 1 月 18 日までです。
映画はルドルフの誕生日から始まりますので 1942 年の 11 月 25 日あたりから 1943 年 11 月にアウシュビッツから強制収容所の監察官として異動するあたり、そして再びアウシュビッツに戻ることになる1944年5月あたりが描かれていることになります。
ちなみにアウシュビッツ強制収容所は 1945 年 1 月 27 日にソ連軍によって解放されています。
それに「観客が感じるのは恐怖か、不安か、それとも無関心か?」なんてコピーが入っていますが、この映画、そうした感じるような映画ではないです。映画から何が感じられるかといったことよりも、よくわからないシーンが多いのでそれらを理解しようと考えることに疲れてしまう映画です。全体に引いたフィックスの画が多くて人物を掴みづらく、流れも断片的ですので集中して見るのはかなり難しいです。
集中して見られる映画でければなかなか感じる映画にはならないということです。
スポンサーリンク
考えさせるほどのわかりやすさもなく…
わからなかったシーンのことがウィキペディアのプロットを読んでやっとわかりました。
一番わからなかったのは、ルドルフが子どもたちにヘンゼルとグレーテルの物語を読むシーンに使われていた赤外線カメラで撮られたシーンです。
あれはその間に実際に起きていたことで、ルドルフの家で働いている(働かされている…)ポーランドの少女が食べ物を囚人たちの作業場に隠していたんだそうです。赤外線カメラの映像は2シーンあり、たしかに2度めのシーンではその少女はルドルフの家に戻っていました。
そして、その少女がピアノを弾くシーンがあり、歌がないにもかかわらず字幕がついていましたのでどういうことだろうと考えていたんですが、あれはその少女が囚人の書いた楽譜を拾いそれを演奏していたということです。食べ物を隠していた作業場で缶を拾い中を開けていましたが、赤外線映像ですので楽譜とは分かりませんでした。
ルドルフが子どもたちをカヌーで川に連れ出し、川中で釣りをしているときに何かを手にし、慌てて子どもたちを引き上げ、家で体中を洗わせていました。これはそれらの行為から川に人体のなんらかが流れてきたんだろうとは思いましたが、なにせ引きの画のままですので何を手にしたかまでははっきりしませんでした。骨ですかね。
ルドルフのオフィスに女性がやってきて髪を下ろして座っているシーンがあり、ああ、そういうことかなとは思いましたが、続くシーンはその場のシーンではなく、ルドルフが地下室のような部屋に移動して自分の股間を洗うシーンでした。こういうシーン構成があざとく感じられる映画です。それにその間に挟まれる移動のシーンが、長々と地下道のようなところを歩いて移動していくシーンでしたのでよけいにわからなくなります。
ヘートヴィヒの母親が何も告げずに去っていったのは耐えられなかったんでしょう。その前夜、沈痛な面持ちの母親のシーンがありました。
この映画のつくりでこうしたことが何の事前情報も得ずしてわかるんでしょうか。
スポンサーリンク
関心領域、Interessengebiet、The Zone of Interest
という映画ですので、これを描きたいという思いが感じられない、どうわかりにくく見せようかと考えられているような映画に感じます。
見る前からわかっていることを2時間延々と見せられる映画ということかと思います。
ところで、この「関心領域」と訳される Interessengebiet という言葉は、ナチスドイツがアウシュビッツ強制収容所の周囲の親衛隊(SS)のために確保され地域を呼ぶ言葉として実際に使われていたようです。

By SS – http://auschwitz.org/en/gallery/historical-pictures-and-documents/archive-documents,2.html, Public Domain, Link
SS, Public domain, via Wikimedia Commons
このリンク先を読んでふと思ったことは、パレスチナのユダヤ人による入植地って、この Interessengebiet と同じじゃないでしょうかね。
ちょっと俳優さんのことも書いておきます。
それなりに知性的な人物に描かれていたルドルフ・ヘスを演じていたのは「白いリボン」のクリスティアン・フリーデルさんです。
ラストシーンに階段の途中で吐いていたのは多少の良心があるという意味なのか、もしそうであるのならジョナサン・グレイザー監督の考えは間違っています。人間は自らの悪行に罪悪感など感じられずに生きられる存在です。
ヘートヴィヒ・ヘスを演じていたのはザンドラ・ヒュラーさん、この俳優さんはうまいですね。このヘートヴィヒにも人間の本質的な存在感が感じられました。ただ、やはり「希望の灯り」とか「ありがとう、トニ・エルドマン」といった役柄のほうがしっくりきます。
原作なのか、映画のベースにしている小説があるようです。マーティン・エイミス著『関心領域』、翻訳本が出ています。


